ダウンロード数: 641
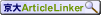
このアイテムのファイル:
このアイテムは一定期間後に公開されます。
公開日については,アイテム画面の「著作権等」でご確認ください。
公開日については,アイテム画面の「著作権等」でご確認ください。
| タイトル: | ドイツ啓蒙主義における「道徳性」と「美的なもの」--レッシング『ハンブルク演劇論』74篇-79篇を手がかりにして |
| その他のタイトル: | „Die Moralität" und „das Ästhetische" in der deutschen Aufklarung: Anhänd der HamburgischenDramaturgie (St. 74-79) Lessings |
| 著者: | 藤井, 俊之 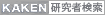 |
| 著者名の別形: | FUJII, Toshiyuki |
| 発行日: | 20-Dec-2009 |
| 出版者: | 京都大学大学院人間・環境学研究科 |
| 誌名: | 人間・環境学 |
| 巻: | 18 |
| 開始ページ: | 121 |
| 終了ページ: | 136 |
| 抄録: | 18世紀ドイツ啓蒙主義の時代, 民衆の趣味の陶冶をこととしてきた劇場は, それまでの「教化機関」としての役割を抜け出し, 美的快楽に奉仕するそれ自体で自律した領域となった. 演劇の関心事が「道徳性」から「美的なもの」へと向かう過渡期において, ドイツの啓蒙主義者たちがどのように思考し, 解決を探ったのか. 本稿が主題とするのはこの点である. この時代に道徳の擁護を行ったという点で一つの症候を示すG. E. レッシングの演劇論, 特に彼の著作『ハンブルク演劇論』における悲劇論に焦点があてられる. その際, 彼の悲劇論の背景をなすゴットシェート, ニコライ, メンデルスゾーンといった同時代の人々とレッシングとの関係をも視野に納めることで, 「道徳性」と「美的なもの」との対立を, レッシング一個人だけでなく, 時代的文脈からも概観する. Im 18 Jahrhundert, dem Zeitalter der deutschen Aufklärung, hat sich das Theater, das sich als moralische Anstalt mit der Bildung des Volksgeschmacks zu beschäftigen hatte, in eine autonome Institution gewandelt, die der ästhetischen Lust dient. Die vorliegende Abhandlung soll beobachten, wie die deutschen Aufklärer in dieser Übergangszeit von der Moralität hin zu dem Ästhetischen dachten und nach einer Auflösung suchten. In unserer Untersuchung spielt G. E. Lessing die Hauptrolle und steht seine Theorie des Trauerspiels, die besonders in der Hamburgischen Dramaturgie entwickelt wird, im Brennpunkt der Diskussion. Dabei wird diese Konfrontation der Moralität mit dem Ästhetischen nicht nur am Beispiel des Lessingtextes, sondern auch im zeitlichen Kontext behandelt, indem das Verhältnis zwischen Lessing und seinen Zeitgenossen (Gottsched, Nicolai und Mendelssohn usw.) berücksichtigt wird. |
| 著作権等: | 許諾条件により本文は2027-07-01に公開(2017-06-29追記) ©2009 京都大学大学院人間・環境学研究科 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/109781 |
| 出現コレクション: | 第18巻 |
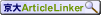
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

