このアイテムのアクセス数: 809
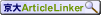
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| asia19_2_103.pdf | 553.15 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | <論文>キリスト教は日本人に親しまれているか? --西田幾多郎の〈日本文化の問題〉から見て-- |
| その他のタイトル: | <Articles>Do Japanese Share an Affinity toward Christianity? An Assessment from the Perspective of NISHIDA Kitaro’s Evaluation of Japanese Culture |
| 著者: | 高橋, 勝幸 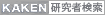 |
| 著者名の別形: | TAKAHASHI, Katsuyuki |
| 発行日: | Mar-2021 |
| 出版者: | 「アジア・キリスト・多元性」研究会 |
| 誌名: | アジア・キリスト教・多元性 |
| 巻: | 19 |
| 号: | 2 |
| 開始ページ: | 103 |
| 終了ページ: | 118 |
| 抄録: | 和辻哲郎が言い始めたとされる「もの」と「こと」を念頭に見て行くと、東西の思想対立が浮き彫りになってくる。これまで論理的・科学的な欧米思想を是とする「もの」的思考を優位として来た西洋の文化、宗教、道徳、生活習慣が途上国に押し付けられてきた。それはまた、途上国を西洋に追随させ、植民地支配をも是としてきたが、人類を豊かにするはずの科学技術で人類が滅ぼされようとしてきた。この地球規模の問題の行き詰まりは既に多くの著作にあるが、それまで非論理的として一段低いものとしてきた東洋の「こと」的思考に頼らざるを得なくなってきている。すなわち欧米思想を中心として優位・絶対と見る限り、欧米人のキリスト教宣教師は科学的な思考を上位とする目線で東洋的・日本的な西田哲学までも非論理的で一段低いものと見るために「(論理的に)限界がある」として軽視してきた。このため、キリシタン時代の適応主義にも批判的になってくる。しかし、21世紀は単独の宗教では諸問題に答えられなくなってきて、対話・邂逅の道が求められるようになってきた。邂逅の道「対話の基本」は双方が対等で自由な立場において成立するが、一方的な押し付けでは支配者と被支配者の関係でしかなく、対話そのものが成立していなかった。キリシタン時代のその土地の良いものをキリスト教の中に取り入れて行く適応主義は別だが、明治維新以降のキリスト教は西洋中心の科学的な思想に偏って来たがため、「こと的」思想を生きる日本人には馴染まないことを訴えたい。 |
| DOI: | 10.14989/264513 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/264513 |
| 出現コレクション: | 第19号第2集 |
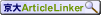
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

