このアイテムのアクセス数: 682
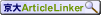
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| nobunken_31_001.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | <研究ノート>稲作の天水農耕地帯への波及 --中国の新石器時代から古代王朝までを概観して-- |
| その他のタイトル: | The Role of Rice Cultivation for the Development of Ancient Kingdoms in China: Discussion with Archeological Evidence in China |
| 著者: | 池橋, 宏 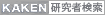 |
| 著者名の別形: | IKEHASHI, Hiroshi |
| キーワード: | 水田稲作 中国考古学 中国の新石器時代 竜山文化 中国古代王朝 |
| 発行日: | 25-Jul-2022 |
| 出版者: | 農耕文化研究振興会 |
| 誌名: | 農耕の技術と文化 |
| 巻: | 31 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 14 |
| 抄録: | 今世紀に入り洛陽郊外の二里頭の夏の王都とされる遺跡からかなりの量の米が出土し、またこの遺跡に隣接する殷の偃師商城の祭祀遺跡から大量の炭化米が出た。これらの知見により、黄河流域に栄えた古代の王朝の地域では主にアワやキビなどの天水農耕が行われていたとする従来の見方には再検討の余地があろう。ここでは中国語で出版された、淮河上流域や漢水上流域の考古学的研究、および山東省で発達した大汶口文化の晩期の西方への展開などの報告も参照し、水田稲作が新石器時代の晩期からアワやキビの農耕地域へ波及したことを示す記事に注目した。さらに、稲作を基礎とする良渚文化の大汶口文化への影響、大汶口文化の竜山文化への発展、および良渚文化の夏王朝への影響をたどり、これらの歴史の背景にあった淮河中・下流域の可住地の拡大と水田稲作の役割に注目した。そして稲作の波及は古代王朝の成立にも寄与した一要因であったと考察した。 |
| 著作権等: | 許諾条件により本文は2023-07-25に公開 |
| DOI: | 10.14989/nobunken_31_001 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/278684 |
| 関連リンク: | https://www.nobunken.org/31-2022-1 |
| 出現コレクション: | 第31号 |
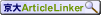
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

