このアイテムのアクセス数: 451
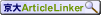
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| shirin_085_5_637.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
| タイトル: | <論説>「復元」された測量と近世山論絵図 : 北摂山地南麓地域を事例として |
| その他のタイトル: | <Articles>Indigenous Land Surveyor and Mapmaker in Early Modern Japan : With Special Reference to the Cases of Boundary Disputes in Northern Osaka |
| 著者: | 鳴海, 邦匡 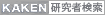 |
| 著者名の別形: | NARUMI, Kunitada |
| 発行日: | 1-Sep-2002 |
| 出版者: | 史学研究会 (京都大学文学部内) |
| 誌名: | 史林 |
| 巻: | 85 |
| 号: | 5 |
| 開始ページ: | 637 |
| 終了ページ: | 678 |
| 抄録: | 十八世紀後期における小物成山の利用を巡る訴訟過程で、摂津国豊嶋郡の村々が立会絵図を測量図として作製することとなった。大坂町奉行所での指示を受け、村々は隣村の職業絵師を雇ったうえ、まず論点の現地調査を行っている。その後、村役人らの手により一七八三年からの三年で計二十四日間かけて実施された論所の測量は、「小丸」と称される磁石方位盤などを用い測量地点間言に距離と方位を測り進むものであった。この測量は、論山の山裾付近、山の周囲、山内の順に作業が進められ、それは計二十五ヶ所の測量区間で約二十八キロにもおよんでいる。特に山内を「立縄」や「横縄」と称して縦横に実施した測量は特徴的であり、論山内の位置付けと絵図の正確さを向上させるための役割を果たしていた。これらの作業を村役人や絵師が担っていたことは、当該期における地図測量技術の農村社会への広がりを示すものであり、地図作製の実態を知る貴重な資料となっている。 The purpose of this paper is to show the process and indigenous techniques of land surveys on mapmaking at the middle stage of the Tokugawa era. The main objects of study are the documents created for territorial claims in disputes over the village common in northern Osaka. When this boundary dispute happened, the authorities ordered the villagers to make the map. First, the 'peasants would try to survey the land at issue. The compass they used had the capability of measuring angles to an accuracy of three degrees. Then, a professional painter would draw a map on basis of the data and his observations of the site. These cartographic devices were gradually adopted nationwide to meet the demands of territorial claims that had increased since around the eighteenth century. |
| 記述: | 個人情報保護のため削除部分あり |
| DOI: | 10.14989/shirin_85_637 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2433/239712 |
| 出現コレクション: | 85巻5号 |
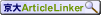
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。

